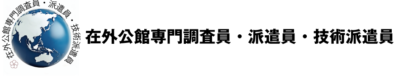専門調査員 チリ大 H・Tさん
チリ共和国

一般事情
チリ共和国
面積:756,000平方キロメートル(日本の約2倍)
人口:約2,086万人(2024年(推定)チリ国家統計局(INE))
首都:サンティアゴ
民族:欧州系87%、先住民系13%
言語:スペイン語
宗教:カトリック(15歳以上人口の42%)、福音派(15歳以上人口の14%)等
外務省HPより

プロフィール
氏 名:T・Hさん
赴任公館:在チリ共和国日本国大使館
職 種:専門調査員
在職期間:2022年10月~2024年10月
*担当事項
チリの内政および外交(総務・政務班所属)
*専門調査員になるまでの経歴、専門(学部、大学院、卒業後)
神田外語大学外国語学部スペイン語学科卒業後、横浜市の総合エンジニアリング企業・千代田化工建設株式会社で主に企業法務部門に従事。在勤中に、中央大学法学部通信教育課程および筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法専攻を修了。同社退職後、外務省本省領事局にて国境を越えた子の連れ去り問題の専門員として個別事案の解決支援にあたる。4年間勤務した後、在チリ日本国大使館に専門調査員として派遣されました。
*専門調査員を知ったきっかけ
外務省本省に勤務していた際、同じ課室の同僚が専門調査員に応募し国連代表部に派遣されたのがきっかけでした。
*専門調査員を希望した動機、期待していたこと
国境を越えた子の連れ去り事案の解決支援にあたっては在外公館の領事の方々とのやり取りが多かったことから在外勤務に関心を抱きました。元々大学の専攻はスペイン語だったことから、応募するならスペイン語圏の公館かな、と思いつつ、子の中学受験やコロナ禍もあり応募するタイミングを見計らっていました。家族帯同だと治安や子どもの教育面も考慮する必要があるため、スペイン、チリ、コスタリカといった比較的安定した国々の募集が出た2022年春募集で応募しました。なお、派遣先となったチリは、学生時代に大学を1年間休学し留学していたことから、30年ぶりの滞在で国がどう変わったのかを知る良い機会だと思いました。
*実際の業務、任期中に書いたレポート、調査出張などについて
(総務・政務班)
日常業務としては、現地新聞や関係政府機関のプレスリリースといった公開情報に基づくチリの内政および外交に関する情報収集が中心で、主要記事の本省への公電や月例報告の作成、また現地日系企業で構成される商工会議所での定期報告などを行いました。また、チリには防衛駐在官(防衛省から外務省に出向し在外公館で防衛に関する事務に従事する自衛官)が配置されているのですが、同じ政務班の所属であったことから防衛駐在官所管業務の支援なども行いました。
(広報文化班ほか)
広報文化班の副担当を兼務していたことから、正担当不在時には広報文化班業務の対応も行いました(主には大使館のSNS記事の翻訳・投稿など)。このほか、大使館主催イベントにおける大使・大使夫人の通訳、大使出張に同行しての通訳、次席が出席する会合に同席してのメモ取り、経済班・領事班・官房班における情報収集や語学面での支援といった館務補助も行いました。なお、翻訳作業が多いことは想定したのですが、思っていた以上に通訳業務が多く冷や汗をかく場面が多々ありました。
(大型ロジ)
着任した時期はコロナ禍がほぼ収束しつつあったことから、天皇誕生日レセプションや自衛隊記念日レセプションなど公邸行事も再開し、全館体制で対応に当たりました。また、任期中に林外務大臣(当時)のチリ訪問、海上自衛隊練習艦隊のチリ寄港という大型イベントがあったほか、岸田総理(当時)の国連総会出席(米国)および南米訪問 (パラグアイ)の応援出張も経験しました。
(研究・調査)
専門調査員に認められている「調査出張」はしませんでしたが、子の連れ去り問題に関し、隣国アルゼンチン旅行時に国際私法会議ブエノスアイレス事務所を訪問して中南米諸国における対応状況の聴取、またチリ法務・人権省の担当部局を訪問しての意見交換を行いました。このほか、任期中に「スペイン法研究」(日本スペイン法研究会の機関誌)、また専門雑誌「ラテンアメリカ時報」に論文を寄稿しました。


*専門調査員後(現在も含め)の仕事と、その仕事(分野)を選んだ理由
帰国後の仕事探しにあたり、在外公館勤務という経験を直接的に活かすという意味で、当初は外務省本省に戻り子の連れ去り問題に再度従事するという選択肢を考えていましたが、担当ポストがいつ空くか見通せない状況でした。他方で、民間企業(「産」)、中央省庁(「官」)の次は「学」に身を置きたいとも思っていたので、その方向でも並行して探しました。そうした中、慶應義塾大学医学部が産学連携共同研究を推進するURA(University ResearchAdministrator)を募集していることを知り応募したところ、企業法務と国際経験を評価され、英文契約担当者として採用となりました。
*将来について
「産」「官」「学」のそれぞれを経験するという希望が叶った一方、外交分野やスペイン語圏との繋がりが途切れてしまったことは少々寂しくもあります。キャリアも終盤に差し掛かり、家庭や子育てとの両立をはかりつつ、これまでの経験や知見をどう収斂させていくのかが今後の自身の課題です。
*専門調査員試験を受けるに当たってどのような勉強をしたか
専門調査員試験は語学と論文の2つからなり、私の場合はスペイン語と派遣先として希望したスペインとチリの国別事情でした。共働きかつ子育てという環境下、自由になる時間は限られるため通勤時間と日曜日の早朝を勉強時間に充てました。スペイン語は、時事問題の出題を念頭に、和文西訳・西文和訳の両方に対応できるよう準備を進めました。国別事情については、外務省サイトのそれぞれの国の紹介ページの内容をベースに整理していったことが効率的だったと思っています。また、語学と論文2カ国分の合計3時間に亘って手書きで回答するため、とにかく手を動かしておくよう意識しました(それでも試験本番ではチリの回答中に手が攣ってしまい焦りました)。
*受験を考えている方へのメッセージ
専門調査員の平均年齢は34歳ですが、私は、50歳を越えての応募でかつ妻子帯同という点で平均的な応募者とは異なる事情がありました。今後はシニア層の応募も増えていくのではないかと思いますが、シニア層の場合、気をつけるべき点が幾つかあるかと思います。まずは、自身の健康です。気候や風土も異なる中、年齢的に無理はききません。健康を保つことが第一です。そして、家族についてで
す。現行の専門調査員の制度では配偶者手当はありますが、子どもに関する手当は皆無です。従って学齢期の子どもを帯同する場合、現地の教育事情(日本人学校・インターナショナルスクールの有無、受入可否、学費など)をできるだけ事前に調べておく必要があります。私の場合、ある程度は調べていたのですが、それでも入学金やスクールバスのバス代などの負担が重く想定以上の大きな出費となりました。
2年の任期を振り返ると、専門調査員という立場で外交の最前線に関わるという貴重な経験ができたといった点を強調する以前に、ともかくも、家族の健康や子どもの教育に四六時中気を遣ったことが思い起こされます。それでも、妻や子どもたちにとっては貴重な経験となったと思っています。
スペイン語圏は在外公館の数に対して応募者が少ない傾向のため倍率は低めで狙い目かもしれません。興味のある方はトライする価値はあります。皆さまのご多幸を祈ります!